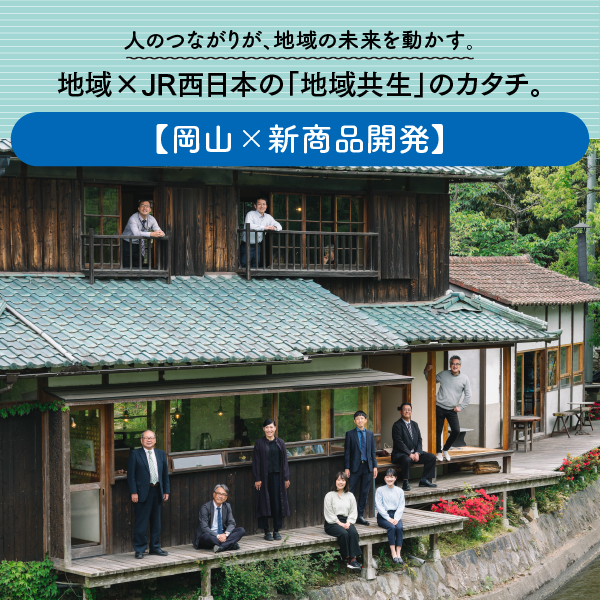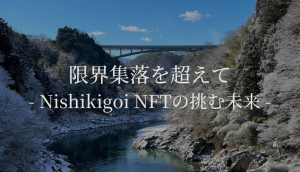このシルエット何県?
皆さんはこのシルエット、何県か分かりますか?
正解:千葉県
千葉県の県章
なお、千葉県の県章は、ハイデリンキックです。
と、いちヒカセンのワタシが申し上げます。#唐突 パート2 pic.twitter.com/200fl1P2gi— らくれさん Racrea Castor (ΦωΦ) ❂FF14Durandal (@RacreaCastor_FF) February 18, 2022
千葉県の由来
1.「千葉」と「ふさの国」の由来
千葉県は、豊かな大地に育まれた農産物に恵まれています。また、全国1位の数を誇る貝塚が示すように、はるか昔の縄文時代から豊かな海の資源にも恵まれていました。
千葉県がこのような自然の恵み豊かな土地であったことは、「ふさ」の字にも表れています。
奈良時代の木簡(もっかん)では、上総のことを「上捄」と書いています。「捄」には「盛る」という意味と、「房をなして稔る果実」の意味があります。
また、平安時代初期の『古語拾遺(こごしゅうい)』には、麻を植えたところよく育ったので、麻の別名である「総」の名をとって「ふさ」の国と名付けたという説話があります。
一方、「千葉」の文字については、『万葉集』の中に、下総国千葉郡の大田部足人(おおたべのたりひと)が天平勝宝7年(755年)に詠んだ歌の冒頭に「知波乃奴乃(千葉の野の)」と記されています。
多くの葉が生い茂ったことを意味する「千葉」も「ふさ」と同じように、千葉県の豊かな土地にふさわしい名前といえるでしょう。
古語拾遺(『千葉県の歴史』資料編古代より転載)
鋸山日本寺展望台
まずは鋸山です。日本寺や地獄のぞきなどで知られた千葉県内有数の観光名所。小さかった頃に一度来た記憶があります。抜群の眺望ですが、高いところが苦手なので少し怖かったかも。ロープウェイもほぼ満員、展望台ほか日本寺も盛況でした。ゴツゴツした岩肌の感触が面白い。帰りは保田まで歩きました。 pic.twitter.com/InFWL3OPY5
— はろるど (@harold_1234) November 27, 2021
参考:千葉県(https://www.pref.chiba.lg.jp/index.html)
参考:鋸山 日本寺(http://www.nihonji.jp/index.html)
参考:DeepExperience(https://www.deep-exp.com/ja)