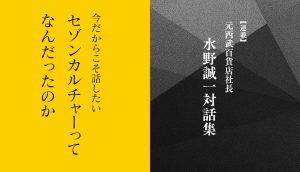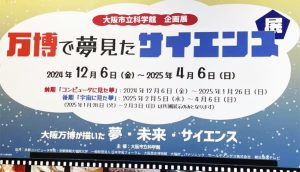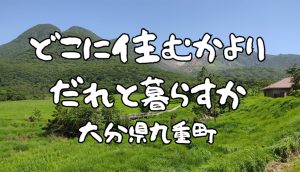今年10月、東日本大震災の津波で大きな被害を受けた宮城県南三陸町に、町の新たなシンボル「南三陸ワイナリー」が誕生した。南三陸の海と山、両方の恵みを活かし、町をまるごと体感できるワイナリー。その代表を務めるのは、静岡県からこの地に移住した佐々木道彦さんだ。震災から10年が経とうとしている今も続く、復興への道のり。そして、この場所に込められた思いとは。
海とともに生きるまち、宮城県南三陸町。
宮城県の北東部、太平洋に面して位置する南三陸町。沿岸部に続くリアス式海岸の景観が美しく、牡蠣や銀鮭などの養殖が盛んな漁業のまち。内陸には標高300〜500mの山々が連なり、山と海が一体となった自然豊かな場所である。

南三陸町は、2011年の東日本大震災で特に大きな被害を受けた地域のひとつ。津波によって甚大な被害を受け、町の60%以上の家屋が全半壊に。当時メディアで報じられた津波の映像は、日本中に大きな衝撃を与えた。特に、骨組みだけになった南三陸町旧防災対策庁舎の変わり果てた姿と、この場所から最後まで避難を呼びかけ続けた職員たちの悲劇には、今も胸を締め付けられる。
その南三陸町で今年、町として初めてとなるワイナリーが誕生した。その名も「南三陸ワイナリー」だ。代表を務める佐々木道彦さんは、東日本大震災をきっかけに東北で生きていくことを決めたという。もともと宮城県には縁もゆかりもなかったなかで、いまワイナリーを立ち上げたのはなぜだったのだろうか。

震災をきっかけに、東北へ。
東日本大震災が発生した当時、佐々木さんは静岡県にいた。もともと楽器メーカーで新規事業や商品開発の仕事をしていた佐々木さんは、震災のあと「自分にもなにかできないか」という思いでボランティアバスに乗り東北へ向かった。
津波で流され、建物の基礎と瓦礫だけになった沿岸部の様子を見たとき、瓦礫の撤去や建物の復旧は進んでも、震災前のような“まち”は戻ってこないかもしれない――佐々木さんはそんな危機感を感じたという。実際、この震災を機に県外やほかの地域へ移住した人も多い。“まち”としての賑わいを再び取り戻すハードルは相当高いという現実を、そのとき目の当たりにした。

現地でのボランティア活動は、佐々木さんにとって新たな発見と感動の連続だった。「東北のために力になりたい」という同じ志を持った仲間とともに、汗を流しながらの作業。そして夜は、年齢も経験もさまざまなボランティア仲間や地元の人たちと飲みながら語り合う。何度か活動を重ねるうちに、佐々木さんのなかで「東北に関わり続けたい」という思いは強くなっていった。
そして同時に、ボランティアとして地域に関わるなかで「“まち”の復興のためには、新しい産業や事業が必要なのではないか」と感じるようになった。それまで新規事業に携わってきた経験を東北のために活かしたい――そう考えた佐々木さんは、ついに長年勤めた会社を退職し、仙台への移住を決意する。2014年のことだった。
この“移住”という大きな決断の背景には、震災ボランティアを通じて、地元の人の思いに触れたことが大きかったと話す。
佐々木さん「津波で大変な思いをした方や家族が亡くなった方の話を聞いたときに、いまの仕事を辞めてでも、もっとこの地域や人と接する仕事がしたいと感じたんです。もちろん長年勤めた会社を辞めるのは悩みました。でも、現地でもっと大変な目に遭ってる方々のことを思えば、自分が会社を辞めるなんて全然大変なことではなかったし、生活面で困ることはあるかもしれないけど、それよりも自分が納得する仕事をやりたいという思いでした。それを家族にも伝えたら了承してくれて、一緒に移住することにしたんです」
ワインとの出会い。
そうして仙台へやってきた佐々木さんは、衣食住に関わる仕事をしようと住宅・建材メーカーで働き始めるが、思い描いていたような三陸沿岸部での仕事は少なかった。「津波の被害が大きかった沿岸部の地域に直接関われるかなと思って行ったのですが、結果的にあまりそういうところには力を入れていなくて。当時は会社で働きながら、なにができるかをずっと探してたような気がします」と振り返る。

そんな思いを抱えるなかで、伝統的な職人技術を活かしたものづくりをしている企業へ転職し、そこでワイングラスの商品開発に携わることに。それをきっかけにワイン会にも参加するようになり、ワイン関係者との交流も増えた。そうするうちに、ワインの魅力と可能性を感じるようになる。
佐々木さん「当時はほかのグラスも作っていましたが、ワイングラスは必ずペアで買われるんです。ワインはだれかと楽しむためのものというのをすごく感じました。しかもワイン自体、水は加えずブドウだけで作るお酒なので、その地域で育てられたブドウの特徴が出やすいんです。だから、より地域を語れるお酒だということも知りました。世界的にも六次産業化の代表的な存在として地域を元気にしているワイナリーもたくさんあったので、自分も『ワインでなにかできないか』と考えるようになりました」
地域をつなぐワイナリーを作りたい。
それからワイナリーを作ることを漠然と考え始めた佐々木さんは、ワインづくりを学ぶため、宮城県内初のワイナリーとして2015年にオープンした「秋保ワイナリー」で醸造を手伝わせてもらうことに。そうしてしばらく秋保ワイナリーへ通うなかで、当時すでに動き出していた「南三陸町ワインプロジェクト」の存在を知る。しかもちょうど新たなメンバーを募集しているという話を聞き、すぐに応募を決めた。

南三陸ワインプロジェクトは、南三陸町でのブドウ栽培やワインの生産を目指し、2017年に立ち上げられた。そもそもの始まりは、秋保ワイナリーで生産していたシードルの原料として、南三陸町のリンゴを使用していたこと。そのつながりで、2016年に秋保ワイナリーから南三陸町の農家へワイン用のブドウの木が寄贈された。このブドウが町内で順調に生育したことで、いずれは南三陸町でもワインを生産して町を盛り上げようと立ち上がったプロジェクトだった。

2017年にプロジェクトはスタートしていたものの、事業化の道がなかなか見えないなか、このとき本格的に事業として推進していくメンバーを追加で募集していたところだった。三陸沿岸部を支援するために東北への移住を決め、ワイナリーを作ろうと思い始めていた佐々木さんにとっては、運命的な出会いだった。
佐々木さん「『ワイナリーをやりたい』と思って行動し出したときに南三陸の話があって、すぐに参加を決めました。でもそれが沿岸部じゃなくて内陸部のどこか違う、津波と関係のない場所だったら、そこまで思わなかったかもしれないです。すぐにやろうと思って行動できたのは、南三陸だったからですね。やっぱりそのために東北に戻って来たし、ワインに合わせる南三陸の食も本当においしいので、すごく可能性を感じました」
仮設の工場をワイナリーに改装! 本当の復興はこれから。
そうして2018年の秋から、佐々木さんはこのプロジェクトに参加した。プロジェクトが立ち上がってからしばらくの間はワインの醸造技術を学ぶための研修期間が長く、南三陸での動きが見えづらかったこともあり、地元の人からは「本当にワイナリーができるのだろうか?」という声もあったのだそう。
そんななかで佐々木さんが加わり、徐々にワインづくりの準備も整ってきたところで、地元の人にもプロジェクトを知ってもらおうと、震災以降、町内で月1回開催されている「福興市」に出店することに。毎月、南三陸で穫れる旬の海産物が並ぶ福興市で、ワインと一緒に南三陸の食を楽しんでもらいながら、自分たちの活動やワインのおいしさを伝えるようになった。そうして少しずつ活動の様子が伝わっていくと、町の人の協力も得られるようになり、ワイナリーのオープンへ向けてさらに加速していった。

役目を終えた水産加工場を、ワイナリーに。
特に大きかったのは、南三陸ワイナリーが作られたこの場所との出会いだ。実はここは、もともと震災後に仮設の水産加工場として使われていた場所。昨年、新しい建物への移転が決まったあと、佐々木さんのもとに「ワイナリーとして使ったらどうか」という連絡が届いたのだった。
もともと“海が見えるワイナリー”というコンセプトを掲げていた佐々木さん。しかし、理想を叶える場所がなかなか見つからず、まさに悩んでいたところだった。この水産加工場なら、ワインを醸造するための廃水設備も十分整っているし、新築で建てるよりもはるかにコストを抑えられる。すぐにこの場所にワイナリーを作ることを決めた。

こうして再び運命的な出会いに恵まれたが、もちろんそれは「ただ運が良かった」ということではない。佐々木さんをはじめとするプロジェクトメンバーが、この地域で着実に積み上げてきた信頼と期待があったからこそだろう。この水産加工場との出会いも、そんな日々の活動の積み重ねだったと振り返る。
佐々木さん「最初は町のいろんな場所を探しまわって、『どこにワイナリーを建てよう』『どこに畑を広げよう』と何ヶ月も悩みました。海に近い場所が見つからなかったり、資金集めの方法にも苦労していて。でも、イベントでワイナリーを作りたいんだっていうことを町の人にアピールしていたからこそ、良い場所が出てきたときに声をかけてもらったり、町内の方にもふだんから気にかけていただいて、最終的に本当に良い場所に巡り会えました。最初は半信半疑だった地元の方もすごく期待してくれているのを感じましたね」
そして今年5月からは、ワイナリー実現へ向けたクラウドファンディングにも挑戦し、200万円の目標金額も大幅に達成。改装工事の予算も限られていたなかで、県内や東北在住者限定でボランティアを募り、可能な限りDIYで工事は進められた。週末に行われる塗装や看板作成などの作業には毎回約10名ほどのボランティアが参加し、ついに今年10月、多くの人の手によって南三陸ワイナリーは完成し、無事オープンを迎えた。

まち全体をつなぐワイナリーの誕生
完成した南三陸ワイナリーは、ワインの醸造を行う“醸造棟”、ワインの販売や試飲を行う“ショップ棟”、そして志津川湾を望む絶景が広がる“テラス棟”の3つの棟で構成されている。

ワイナリーから少し離れた山の山頂にはブドウ畑が作られ、そこで育ったブドウが、海に面したこのワイナリーで醸造される。そうして南三陸の山と海の恵みを活かしたワインが作られると同時に、ワイナリーを訪れた人には、海中熟成させるワインを海へ沈めたり、ブドウの収穫体験などを通して、南三陸全体を体感してもらう。そんなふうに、この南三陸ワイナリーはあえて町全体を使うように考えて作られているという。

「まだ町が整備されただけ。賑わいを取り戻したい」
そして、このワイナリーを通じて佐々木さんが目指すのは、南三陸の地域のつながりや新たな賑わいをつくること。震災から10年が経とうとしているなかで、本当の復興はこれからだ、と話してくれた。
佐々木さん「南三陸町ではこないだ『震災復興祈念公園』ができて、復興関係の予算でやってきた事業の終わりがやっと見えてきたというところ。でもそれって、ただ単にインフラ整備をしただけで、本当の意味での賑わいはまだまだ戻っていないんです」

佐々木さん「人がいちばん多かった中心部には、今は家も建てられないし、新しい宿泊施設も建てられなくなっていて。昔だったら居酒屋や宿泊場所もあって、地元の漁師さん同士も交流するし、旅行者も飲み屋で地元の人と話したりしていたのが、今はもう全然なくなってしまった。地元の人からも、さみしいっていう声はよく聞くんですよ。しかも人口減少がどんどん進んでいて、いまから新たに賑わいを作っていかないと、本当にこういう小さい町はなくなってしまうんじゃないかと感じています。だから、10年目を迎える前に南三陸ワイナリーができてすごく良かった。本当の復興はこれからだと思っています」
震災以降そうした厳しい状況は続いているが、新たに南三陸ワイナリーがオープンしたことで「お客さんが増えたよ」という地元商店街からの声も聞かれるようになり、町に新たな賑わいが生まれつつあるのを感じている。販売しているワインの売れ行きも好調で、新型コロナの影響で多めに残っていたワインの在庫も、すでにほぼなくなってしまったとか。

「おいしい」がみんなをつなぐ。
とはいえ、南三陸ワイナリーの挑戦はまだ始まったばかり。オープン後には、新たに「南三陸のみんなとおいしくなりたい」というコンセプトを掲げ、走り出した。佐々木さんは最後に、このことばに込めた思いとワイナリーのこれからについて、こんなふうに語ってくれた。
佐々木さん「やっぱりみんな美味しいもの食べたいし、それをきっかけにいろんな話もしたいはずで。そういうきっかけがないと、なかなか人はつながっていけないと思ったんです。それにはワインが本当に最適で、おいしいものも人もつなぎ合わせてくれる。そして、ブドウの収穫や海中熟成のような体験もあわせて楽しんでもらって、町全体を大きく使ってやっていきたいと思っています。町外の方にも、さんさん商店街の買い物ついでじゃなくて、南三陸のまちも食も体験して、もっとここで時間を過ごしたいと思えるようなことをたくさんやっていきたいですね」

“まち”は人がいなければ続いていかない。長い歴史のなかで、この地域が何度も大きな津波の被害を乗り越えてきたのは、自然とともにこのまちで暮らし続ける人びとがいたからだ。
だからこそ南三陸ワイナリーは、地元の人も町外の人も関係なく、これから「おいしい」でみんなをつなぐ拠点になっていく。震災を経てこのまちと出会った佐々木さん自身がいま、そうして人と人、人と地域をつなぎ、この場所から新たな出会いと賑わいを生み出そうとしている。
みんなが笑顔になる、南三陸の豊かな食とワイン。その新たなマリアージュと南三陸のいまを、ぜひ多くの人に体感してみてほしい。