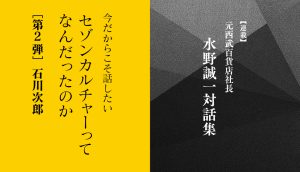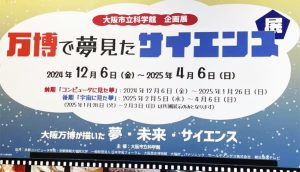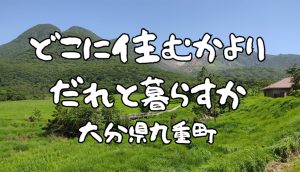りんご飴やりんごを使ったオリジナルスイーツ等を販売する新店舗『ポムdeなっぷる』をオープンします。
まるで絵本から飛び出してきたような外観とアンティークを基調とした店内。赤く実をつけた本物のりんごの木をシンボルツリーに水色の扉が目印です。
店舗情報
所在地:愛知県額田郡幸田町深溝楠木3
営業時間:午前11時~午後5時(定休日:火・水曜日)
販売品目:りんご飴、産地直送りんご、りんごを使ったスイーツ、りんご等果物のジュース、幸田町特産品を使ったスイーツなど
ホームページ:https://napple-apple.jp
オンラインショップ(ポムdeなっぷる):https://napple.shopselect.net
公式インスタグラム:@ringo.napple ( https://www.instagram.com/ringo.napple )
りんご飴「ぽっぷる」
また、「両親や友達におすそ分けしたのですが大好評でした」や「孫に見せた途端に目を輝かせて大喜びでした。」、「友達から頂いてとても美味しくてリピートしました。」など、たくさんの声をいただき、りんご飴を通して笑顔の連鎖が広がっています。
食べたら人に教えたくなる。美味しさを伝えたくなる。ポムdeなっぷるのりんご飴「ぽっぷる」は人と人の心を繋ぐスイーツです。
りんご飴だけじゃない!巨大いちご飴!
販売開始:2023年1月20日(金)
販売価格:600円(税込み)