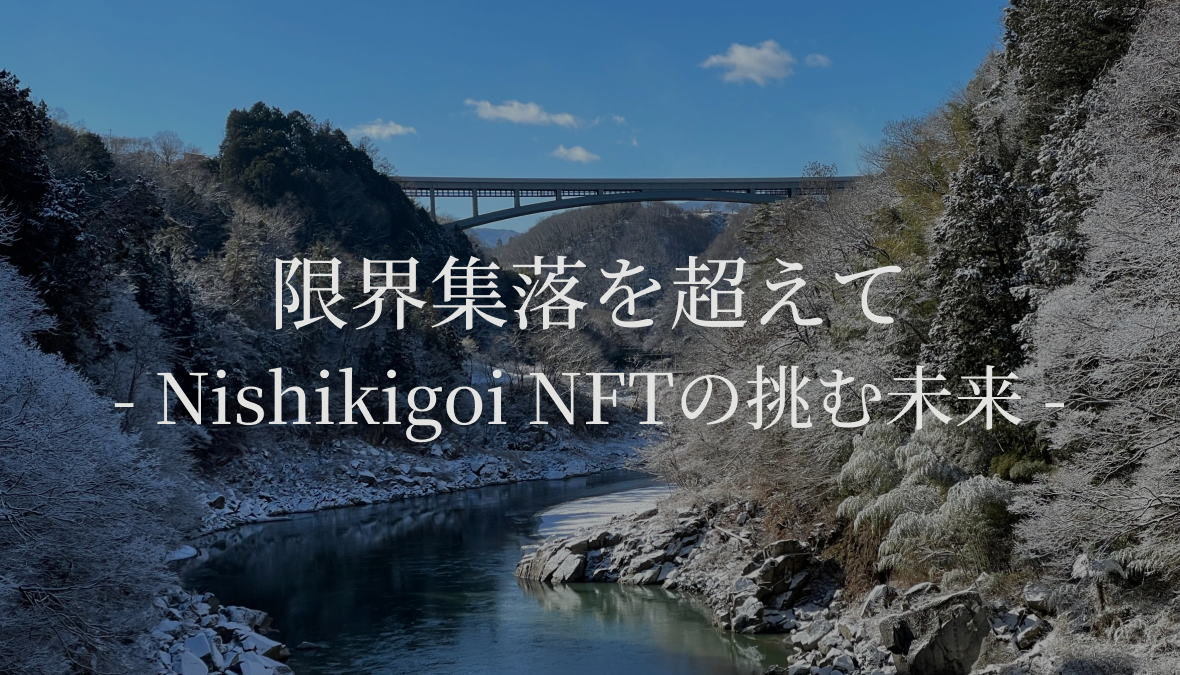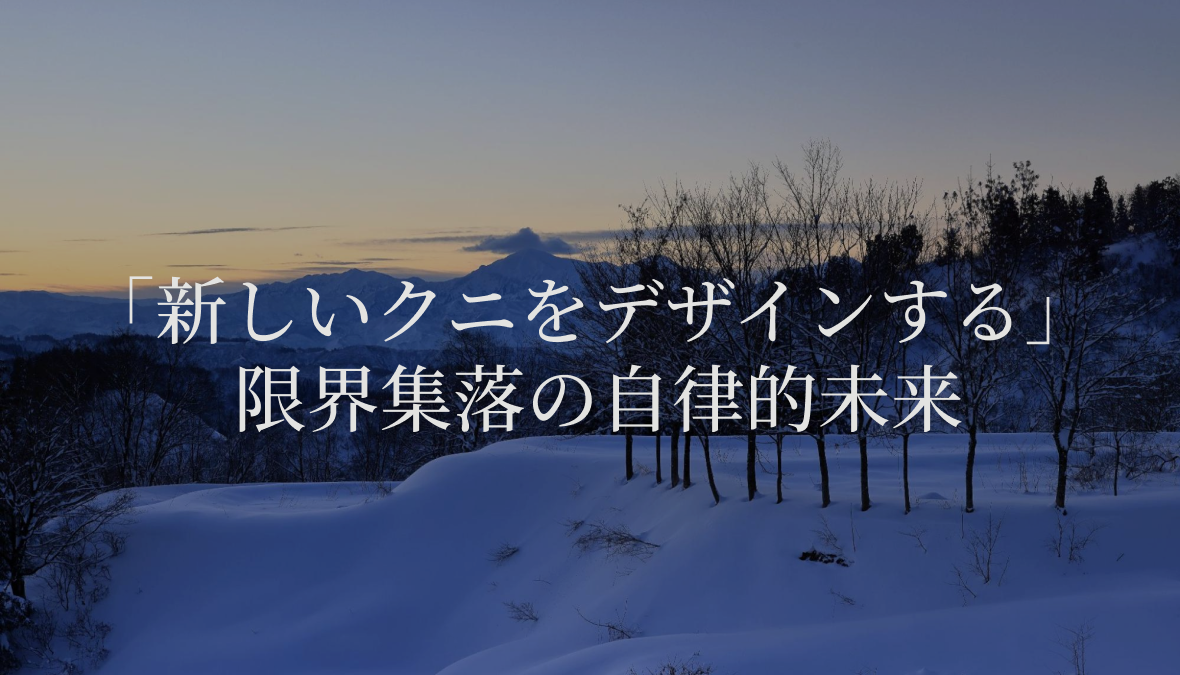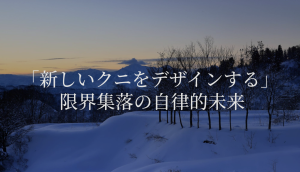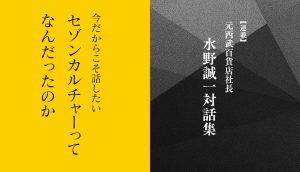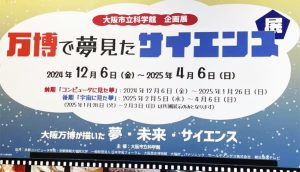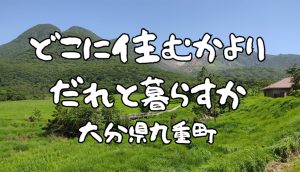かつて新潟県山古志地域(旧山古志村)は、2004年の中越地震による甚大な被害を受けました。そして、震災から半年後の2005年4月、山古志村は長岡市に編入合併されることとなりました。しかし、その精神は消えることなく、今もなお新たな形で息づいています。その象徴ともいえるのが、「ネオ山古志村(旧:山古志DAO)」というコミュニティです。
NFTというデジタルツールを活用しながら、地域と人々のつながりを再構築しようとする試みが始まって3年。果たしてこの「村」はどこへ向かおうとしているのか──。今回は、ネオ山古志村の発起人であり、Nishikigoi NFTのファウンダーである竹内春華さん、そして彼女のマネージャーであるデジタル村民・りーまんさんにインタビューを行いました。彼らのビジョンや、これまでの挑戦、そして今後の展望をお届けします。
このタイトル「新しいクニをデザインする」は、単なる比喩ではなく、ネオ山古志村が本当に目指している未来を象徴する言葉です。新潟県の旧山古志村から生まれたこのコミュニティは、行政区画の枠にとらわれず、地域の可能性を最大限に引き出す新しい形を模索しています。今回の記事を通じて、ネオ山古志村の本質に触れ、その挑戦の意義をダイレクトに感じていただければと思います。
地縁、血縁を超えて
クリプトヴィレッジ:そもそも「ネオ山古志村」はどんなプロジェクトでしょうか?背景や設立に至った経緯について教えてください。
竹内:ご存知の方もいるかもしれませんが、山古志は20年前の中越地震によって全村避難を経験しました。当時の住民は約2,200人。しかし、三年半をかけて戻ってきたときには約1,700人に減少していました。
それでも山古志をもう一度盛り上げようと、住民の皆さんが主体となってさまざまな取り組みを行いましたが、人口減少は止まりませんでした。そのときふと思ったんです。「私たちは、ただ人口の増減のために山古志をつくってきたわけではない」と。これまで山古志を支えてきたのは、現地に住む人々だけではなく、山古志出身で外の世界へ羽ばたいた人や、山古志に関わり続けてくれる人々でした。そうした「山古志DNA」を受け継ぐ仲間とともに、これからも地域をつくっていきたい。そう考え、新たな取り組みとして立ち上げたのが「仮想山古志プロジェクト」、現在のネオ山古志村の前身となるプロジェクトです。
この「仮想山古志プロジェクト」は2020年頃に発足し、「地縁や血縁にとらわれない新たな自治圏をつくり、山古志の未来を切り拓く」ことをテーマに掲げました。しかし、地域の枠を超えた仲間を見つけたとしても、それをどのように受け入れ、つながりを可視化するのか。そのためのシステムやツールを模索していたのです。
NFTとの出会いが、山古志の新たな可能性を切り開きました。2021年12月、山古志の象徴である錦鯉をモチーフにした「Nishikigoi NFT」を発行し、コミュニティは「山古志DAO」として動き始めました。しかし、「DAO」という概念が一般には馴染みづらい中で、NFTを通じて生まれた新たなつながりを、より明確な形で認め合う仕組みが必要だと感じました。
そこで、山古志DAOそのものをアップデートし、住民だけでなく、デジタル村民も共に未来をつくる場として「ネオ山古志村」へと名称を変更。山古志住民とデジタル村民が話し合い、コミュニティ投票の承認を経て、2024年2月11日、正式にその名を掲げることとなりました。

クリプトヴィレッジ:ネオ山古志村が誕生してもう一年が経つのですね。そもそも「デジタル村民」とは一体何なのでしょうか?デジタル村民と一緒に具体的にどういうコミュニティを作り上げたいですか?
竹内:はい、私たちはNishikigoi NFTの保有者を「デジタル村民」と呼んでいます。現在、その数は1,800人ほどになりました。そして、少しずつですがデジタル村民の方が実際に山古志に訪れて、住民の皆さんと他愛もない話をしたり、近所付き合い、親戚付き合いのような関係性が築き上げられています。
そのため、「ホストとゲスト」という関係ではなく、みんなで山古志をつなぐ一員であるという感覚が、少しずつ山古志の住民の間にも芽生え始め、デジタル村民の方々の中にも広がりつつあります。目指しているのは、単なるNFTの保有者と地域住民という関係ではなく、互いに支え合いながら山古志の未来を共に創っていくコミュニティです。そんな共創型の関係を築いていきたいと考えています。

クリプトヴィレッジ:ネオ山古志村が掲げる「旗印」について教えてください。
竹内:ネオ山古志村の旗印については、気がつけば1年ほど議論を重ねていました。「ああでもない、こうでもない」と模索しながら、最終的に山古志地域の住民が掲げた「つなごう山古志の心」という言葉を、少しアップデートする形で旗印とすることに決まりました。
最初からこの言葉が候補だったわけではありません。住民やデジタル村民との対話、実際に山古志を訪れた経験を通じて、地域の人々が紡いできた言葉の本質的な意義が腑に落ちていったのです。「こういう思いが込められていたのか」と実感できたからこそ、単なる継承ではなく、大切にしながら進化させる形で旗印を定めることができたのだと思います。
クリプトヴィレッジ:実際にデジタル村民はどのような活動をされているんですか?
竹内:ネオ山古志村が立ち上がってからの1年は、リアル山古志住民とデジタル村民がともに地域に関わり、課題に向き合いながら活動してきた期間でした。イベントや事業、景観整備、維持管理にリアル住民も主体的に参加し、デジタル村民は山古志に足を運びながら、各集落や団体と交流を深め、地域が抱える本質的な課題を抽出。週一のミーティングで議論を重ねながら、解決策を模索してきました。
具体的には、山古志小中学校の合同運動会の応援、山古志のお父さん、お母さん方がやっている直売場祭りのサポート、牛の角突きのファンクラブ運営、そして10月23日の中越地震メモリアルデイにも携わってくださいました。一緒に悩み、一緒に挑戦し、一緒に成功を分かち合うことで、リアル山古志住民とデジタル村民が「共に地域をつくる仲間」としての意識が少しずつ育まれた1年意識を育んだ1年だったと感じています。

クリプトヴィレッジ:デジタル村民が山古志の運動会の応援に行くってすごいことですね。
竹内:そうなんですよ。でも、最初からこういう関係だったわけじゃなくて、山古志の人たちにとって「デジタル村民」って、最初はなんだかよく分からない存在だったと思うんです。でも、実際に足を運んでくれて「もっと山古志のことを知りたい」「教えてほしい」と言われると、やっぱり教えたくなるものですよね。最初は「お客さん」という感覚だったのが、今では遠慮のない関係になって、「点と点がつながって、今は面と面がつながってきた」ように感じます。
普通なら、地域の運動会って保護者くらいしか関わらないものですけど、「デジタル村民も一緒にやろうよ!」って山古志の団体から声が上がったり、デジタル村民側からも「子どもたちの取り組みを応援したい!」って声が出たりして、自然と実現していったんですよね。

クリプトヴィレッジ:現在の山古志の課題を教えてください。
竹内:NFTを発行する際、「自助・公助・共助」の共助部分を担ってくれる人をデジタル村民として集めようと思っていたんです。中越地震以降、「自助・共助」の役割を、住民の皆さんも関わる皆さんも、最大限担いながら挑戦を繰り返してきたと思うんです。もちろん、国・県・市による支えがあってのことです。震災から20年、NFT発行から3年が経ちましたが「自助・共助・公助」の在り方も変化しつつあります。
山古志のピンチがさらに深刻化し、予算やマンパワーなど、今、山古志が切実に必要としているリアルな課題もデジタル村民の皆さんに共有しています。信頼しているからこそ、一緒に考えてもらいながら進んでいます。
クリプトヴィレッジ:そんな中でネオ山古志村が目指してるものは?
竹内:語弊を恐れずに言えば、支え合いながら自律したいというのが本音です。実際、どこの自治体でも人口減少による税収の減少やコスパを意識した市政の調整が進んでいます。「山古志村」が、完全に自律するのは難しいとは思いますが、特区のような形で「ネオ山古志村国」のような新たな概念を作れたらいいと思っています。
もし、地方自治体のような権利と義務を持つことができれば、ふるさと納税や企業版ふるさと納税を活用する道も開けます。しかし、行政に全てをお願いするのは難しい部分もあるので、ネオ山古志村の財政面を強化し、そこを投資の場として交渉できるような仕組みを築いていきたいと考えています。もし国家戦略特区やDAO法の整備が進めば、さらに実現に近づくかもしれません。地方自治体の理解を得るための取り組みも大切にしていきたいです。
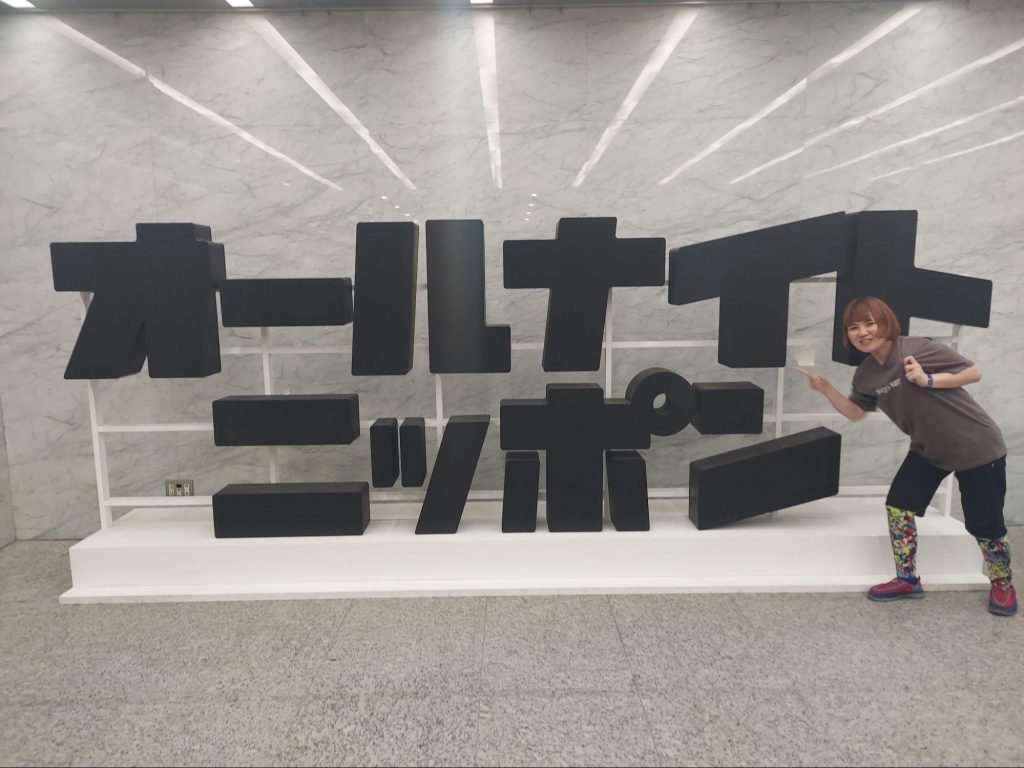
ここからは、竹内春華さんのマネージャーを務めるりーまんさんにお話を伺いました。りーまんさんは山古志のデジタル村民として活動し、ネオ山古志村の取り組みを積極的に支えるメンバーの一人です。昨年には実際に山古志で移住体験をし、その経験を通じて感じた山古志の魅力や、これからのネオ山古志村の可能性について語っていただきました。
他にはないネオ山古志村の魅力
クリプトヴィレッジ:まずはりーまんさんについて教えてください。
りーまん:新潟県の越後湯沢出身で、東京在住デジタル村民のりーまんです。普段はラジオ番組や、音声コンテンツのプロデューサー兼ディレクターなどの仕事をしつつ、ネオ山古志村ファウンダー・竹内春華のマネジメントも担当しています。
クリプトヴィレッジ:竹内春華さんのマネージャーを務めていらっしゃいますが、その経緯と実際の活動内容について教えてください。
りーまん:Nishikigoi NFT発行後から、ありがたくも多くの反響をいただき、竹内さんへの取材・出演・登壇のご依頼もいただいております。当初は全て竹内さん自身が調整をしていました。しかし日々のスケジュール調整に忙殺されているのを見て、マネージャーとして手を挙げさせていただくことになりました。
一番の理由は、竹内さんに「山古志のために使う時間」を確保してもらうためです。現在では新規のご依頼に関しては、竹内さんからメールを転送してもらい、私がスケジュール調整や交渉、その後の掲載日の確認や請求書作成なども行っています。

クリプトヴィレッジ:昨年、山古志で体験移住を経験されたとのことですが、その際に感じた山古志の魅力はどのような点にあると感じましたか?また、どのような人に山古志へ訪れてほしいと思われましたでしょうか?
りーまん:私が移住体験をしたのは山古志の竹沢住宅という施設になります。近隣の方も温かく迎えてくださり、すぐに打ち解けることができました。また、普段は東京で生活をしているせいかもしれませんが、とにかく夜が静かなのが印象的です。
朝は「ウシガエル」の鳴き声で目覚め、E-BIKEで集落内を散策。日中は「やまこし復興交流館おらたる」でワーキングを。テラスに出ると、棚田や棚池に囲まれた景色を一望できます。
今振り返ると、驚くほど作業が進んだ記憶があります。大自然に囲まれた静かな環境は、リモートワークにも適しています。まだ山古志へ訪れたことがない方は、お試し移住体験を利用してみるのも良いかもしれません。
この時の様子をブログ記事に書いたところ、多くの方の反響も頂きました。山古志への移住体験に興味がある方は、ぜひお読みください。(上記画像リンク)
クリプトヴィレッジ:国内では「関係人口×NFT」の取り組みが増えていますが、ネオ山古志村ならではの独自性やユニークさはどこにあると考えますか?
りーまん:私がNishikigoi NFTを購入したのは2021年12月14日、販売開始と共に即購入しました。販売前日にリリースを見かけ、衝撃を受けました。新潟県出身なので山古志の存在自体はもちろん知っています。限界集落と呼ばれる山古志が、最先端のテクノロジーを使って、デジタル住民票の発行。このアイデアに感動したことを今でも覚えています。
NFT自体が注目された当初は、投機的な意味で注目を集めた部分が大きかったと思います。しかし「投機的な意味ではない何か」。今でも残っているNFTプロジェクトにはこの要素があると思っています。
Nishikigoi NFTの価格(フロアプライス)は、デジタル村民は誰も気にしていません。
それでも着実にデジタル村民が増加している理由は、ネオ山古志村の「地方に住んでいても関われる取り組み」にあると思っています。離れていても故郷のために何かがしたいという想いを、山古志に照らし合わせているデジタル村民の方も多いのではないでしょうか。
住民の方は2004年の中越地震の際に、全村避難をした経験があります。住民の方が外に出た経験がある分、外の方を迎え入れてくれる土壌が、山古志の持つ独自性だと思っています。
よそ者のデジタル村民の訪問(帰省)を「お帰り!」と言って迎えてくれる。こうした独特のユニークさも山古志の魅力の一つです。
クリプトヴィレッジ:りーまんさんが思い描く「ネオ山古志村の未来」とは、どのような姿でしょうか?
りーまん:人口減少はこれからも間違いなく進むはずです。ネオ山古志村は移住者を増やすことが目的ではなく、山古志に関わる「関係人口」という協力者をつくること。山古志の伝統文化を、デジタルの力を使って、次世代に繋ぐこと。
昨年、中学生のデジタル村民も誕生しました。今後もどんどん若い世代が増えていき、さらに新しい知恵も集まってくると思います。行政の行き届かないところは、ネオ山古志村という独自の自治権から、地域への予算を捻出する。そんな未来を描いています。

さいごに
野心的とも言えるネオ山古志村が想像する未来。そこには地域に住む人、そしてデジタル村民、それぞれの想いが交差し、新たな可能性が生まれる場所があります。リアルとデジタルが融合し、支え合いながら発展するこの“村”は、ただの地域活性化の枠を超えた、新しい共同体の形を示すかもしれません。これからどんな未来が待っているのか —— その答えを、一緒に創り上げていけたらと思います。
今回のインタビュイーのご紹介
竹内春華
新潟県魚沼市出身。2004年の中越地震で被災し、全村避難となった旧山古志村の住民が暮らす仮設住宅内の山古志災害ボランティアセンターで生活支援相談員として活動。その後、地域復興支援員として、住民主体の地域づくり団体「山古志住民会議」の事務局を務め、地域住民とさまざまな事業を展開しました。2021年4月からは、山古志住民会議の代表を務めています。
𝕏アカウント:https://x.com/yamakoshiMTG
りーまん
2021年12月からネオ山古志村(山古志DAO)デジタル村民。暗号資産やweb3.0、NFT、DAOをテーマにしたポッドキャストも制作。暗号資産やラジオについてはブログでも発信中。
𝕏アカウント:https://x.com/startup3069
暗号資産ブログ:https://startup3.xsrv.jp/
ラジオブログ:https://leaman-startup.conohawing.com/
ぜひフォローをお願いします!
公式ウェブサイト
𝕏アカウント
オンラインコミュニティ
併せて読みたい! Local DAOにまつわる、クリプトヴィレッジの連載記事!