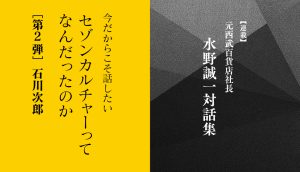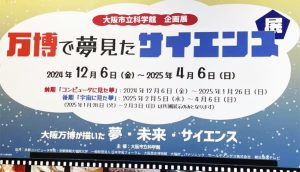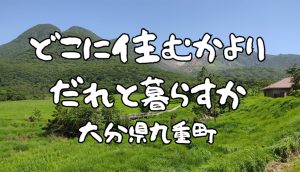日本の各地で生まれている、未来をつくるSDGs的なプロダクトとプロジェクトがあります。勢いを加速させているものからこれから本格稼働するものまで、環境を守りつつ、楽しい持続可能な社会をつくるプロジェクトやプロダクトををご紹介いたします。
mymizu 共同設立者・ルイスロビン敬

水筒のお水がなくなったら、スマホで給水スポットを検索。
発端は2018年の沖縄旅行でのこと。とてもきれいなビーチが大量のゴミで汚染されていたことに衝撃を受けました。そのゴミのなかに、ペットボトルがとても多かったのです。数十年前にはペットボトル飲料も自販機もなかったのに、今では国内で生産されるペットボトルは年間で約252億本。プラスチック問題に直面する今、自分たちの消費行動を変えなくてはと感じました。
そこで仲間と立ち上げたのが『mymizu』という、無料の給水スポットを探せるスマートフォン用アプリです。最近は出かける際にマイボトルを持ち歩く人が増えましたが、ボトルの中身がなくなったらペットボトル飲料を買い足す人も少なくない。身近に給水スポットがあれば、環境にもお財布にも優しいプラスチック削減につながると思ったのです。

給水スポットは大きく分けて3つ。駅や公園の水飲み場などの公共施設、湧き水などの自然スポット、『mymizu』のパートナー店舗であるカフェやホテルです。アプリを通して、ユーザーはカフェなどの新しい場所を発見でき、パートナー店舗はブランドイメージの強化や来訪客の増加といった利点も得られます。2019年にアプリをリリースすると、約6か月で2万5000回以上のダウンロードを記録しました。そして驚いたのは、パートナー店舗の多くが、こちらから営業をかける前に自発的に登録してくれたこと。なかにはユーザーがお店に声をかけてくれたケースもあり、この取り組みへの関心の高さを感じました。今では35か国で約20万か所の給水スポットが登録されています。

今年1月には削減したペットボトルの数やCO2排出量のトラッキング機能も追加。日々の行動が生み出すインパクトを可視化し、給水習慣のモチベーションにつなげたいです。そして、ペットボトルの削減を最初の一歩に、楽しくて魅力的な世界をつくることで人々の消費行動を変えていくことを目指していきます。

このアクションを続けるために、大切にしていることは?
楽しくポジティブな気持ちの、less plastic, more fun!
YATAI CAFÉ 店長・守本陽一

病院の外で医療とつながる、お医者さんのコーヒー屋台。
『YATAI CAFÉ(モバイル屋台de健康カフェ)』は、医者や看護師などの医療従事者が小さな屋台を引いて街を練り歩き、コーヒーを振る舞いながら気軽に健康の話をする活動です。屋台の店員と話をしていたら、実は医者だった。そんな日常生活での医療との偶然の出合いを、兵庫県豊岡市でデザインしています。

この活動を始めたのは、僕自身が地域医療を学ぶ医学生だった頃。当時は地域の人に向けた医療教室を開催していたのですが、参加するのは健康意識の高い人ばかり。医療に関心のない人たちに情報を届けたくても、出会うことができませんでした。そんな時に、医療者がモバイル屋台で東京の街中を巡る活動を知り、豊岡でも屋台を出してみることにしたのです。屋台にはパチンコ帰りのおじいちゃんや学校帰りの学生、お昼休憩の会社員などさまざまな人が訪れます。何げない日常会話から健康についての話題が膨らみ「今度、病院に行ってみようかな」と言ってくれる人も。健康を意識し、医療を身近に感じてくれる人が少しでも増えたらと思いながら、活動を続けています。

実は、この活動を始めた理由はもうひとつ。僕自身が医者以外の"タグ"を持ちたかったのです。現在は総合診療科の医者をしていますが、病院ではどうしても医者や患者という立場を意識してしまいがちに。でも屋台なら気負わずに会話できて、お互いに本音を出しやすい気がします。そんなフランクな関係性を築ければ、信頼や納得の得られる医療にもつながっていくと思うのです。

屋台は不定期開催なのですが、よく遊びに来てくれる人も増えました。井戸端会議のような場になったり、障害のある子どもが居場所として訪れてくれるようになったり。春にはお花見会をしたり、冬にはこたつを置いてみたりと、僕たちもゆるく楽しく活動しています。必要な設備は屋台だけなので、現在は東京都や福井県など日本の各地に活動が広がっています。
このアクションを続けるために、大切にしていることは?
使命感よりも、楽しくワクワクする気持ちで。
UMINARI 共同設立者/ブランディング部 遠山雄大

ゴミのない海を目指し、価値観やシステムを変えていきたい。
『UMINARI』の誕生のきっかけは、代表の伊達敬信が大学2年の時に参加したインターンシップ先で出合った「海のゴミから作られたシューズ」。デザインやストーリーに魅了され、海洋ゴミ問題に関心を持つようになり、ビーチクリーンを始めました。続けていくうちに、海の問題は海の周りだけでは解決できないという課題に気づきました。海の問題は、広くは市場や社会全体につながっていて、生活スタイル、ゴミのサイクルなど、私たちの日常にも密接に関わっています。この課題の解決には、「海の声(UMINARI)」を陸に運び、消費と生産、その他のシステム全体を噛み合わせ、協働させていくことが重要だと感じ、その想いをミッションに掲げ、2017年に同世代の仲間8人で『UMINARI』を立ち上げました。

私たちの主な事業は3つ。1つ目は問題を肌で感じる入り口としてのビーチクリーン活動。2つ目はライフスタイルデザイン事業。海や自然にやさしく、よりサスティナブルで豊かな生活を送るための製品や習慣、価値観を、SNSや「生活塾」というイベントで伝えています。3つ目はエデュケーション活動。小学校や大学の出張授業や若者向けのレクチャーイベント、そして企業向けのワークショップなどを行っています。

今年から、「ライフスタイルデザイン事業」の一環として「粋─IKI─」プロジェクトを始めます。これは2018年夏の旅で感じた違和感が原点。日本中のサスティナブルな製品を探す2週間の旅だったのですが、「世の中の多くの『エコ』を謳う製品は、利便性やデザイン性を犠牲に消費者に”Good”を押しつけている」と感じたのです。でも、日本の風土に合う、粋でサスティナブルな製品にも出合えました。今後は、日本各地の「粋」な製品をオンラインで紹介し、最終的には販売もします。自然も生活も豊かにするライフスタイルの波を、若者から起こしたいです。

このアクションを続けるために、大切にしていることは?
魅力的だから参加したい!と思わせる工夫をすること。
LOOP マーケティング&コミュニケーションディレクター・冨田大介

ゴミを出さないショッピングサービスで使い捨て文化からの脱却に挑戦!
ハブラシ、カプセルコーヒー、ポテトチップスの袋、おむつ……。これらのものは最近まで「リサイクルは不可能だ」と思われてきました。しかし2001年に設立した、私たち『テラサイクル』は、こうしたもののリサイクルを実現し、現在、世界21か国で活動を展開しています。

そんな私たちが2019年1月、世界をあっと驚かせたアイデアを発表しました。それが「LOOP」というショッピングサービスです。「LOOP」の仕組みは、まず、みなさんが普段よく使う食品や日用品を、ガラスやステンレス製の容器に入れて自宅へ届けます。その後、次の注文をお届けする時に使用済みの容器を回収し、洗浄した上でまたどこかの家庭へ届けます。牛乳配達のようなこの仕組みは、2019年5月に米国、フランスで開始し、日本でも今年中に東京を中心とした『イオン』の店頭や、順次さまざまなところでスタートする準備を進めているところです。現在、洗浄・充填設備の準備、容器の開発など、準備の最終段階に入っており、2021年からは全国にサービスを広げていく予定です。日本にはモノを大切に扱う「もったいない精神」が根付いているので、「LOOP」の価値も理解していただきやすいはず、と期待しています。

私たちは「LOOP」を立ち上げた後も、商品ラインナップを増やす努力を続けていきます。その際心がけているのは、シャンプーや食品、飲料など、身近な製品を扱っている大手企業に積極的に声がけをすること。多くの人の暮らしに関連しているものが豊富にあれば、生活に組み込んでもらいやすくなるからです。また米国の調査では、「LOOP」はエコ意識よりも、容器のデザイン性の高さや「日用品がEコマースで届き便利」という利便性に惹かれ、使っている人が多いとの結果もあります。参加の入り口はさまざまでかまわないので、多くの人に利用してもらい、使い捨て文化からの脱却に挑戦していきます!

このアクションを続けるために、大切にしていることは?
消費者嗜好を反映しつつ、使い捨てを脱却すること。
雪国観光圏 代表理事・井口智裕

雪と共生した暮らしを伝える観光で、地域を盛り上げる。
『雪国観光圏』は、新潟県の湯沢町、南魚沼市、魚沼市、十日町市、津南町、群馬県のみなかみ町、長野県の栄村で構成されています。発足は2008年。当時、湯沢町と言えばスキー、南魚沼市と言えばコシヒカリ、といったイメージが強く根付いていて、それ以外の豊かな観光資源が伝わりづらい状況がありました。そこで、周辺の市町村と連携し、「8000年前の縄文時代から雪と共生した暮らしが息づく雪国文化の地」としてエリア全体をブランディングすることにしたのです。

世界でも珍しい「人が住む豪雪地」であるこのエリアには、独自の文化が根づき、いまも伝統的な暮らしが色濃く残っています。たとえば食。雪の下で寝かせ甘みを増した雪下にんじん、冬への備えとして塩漬けにした山菜に干しきのこ、日本酒の寒造りなどは雪国ならではのもの。天然の保湿庫「大根つぐら」や天然の冷蔵庫「雪室」からも、自然を活かす知恵と工夫を学ぶことができます。また、織物。空気に適度な湿り気がある雪国では糸が切れにくく織物づくりに適していて、越後上布、塩沢紬、明石縮など誇れる伝統織物がたくさんあります。雪上に麻布をさらし漂白する「雪さらし」は雪国の冬の風物詩と言えるでしょう。そして、ここは縄文文化発祥の地のひとつ。数多くの縄文遺跡が残されています。自然と共鳴した縄文人の生き方には、持続可能な世界をつくるヒントが詰まっているのではないでしょうか。

こうした雪国の魅力を広く発信するため、『雪国観光圏』では雪国文化博覧会やワークショップの開催、雪国の暮らしに触れられる着地型観光商品の紹介、食と宿の品質認証、3県7市町村の古道や山岳路をつなぐスノーカントリー・トレイルの造成、フリーペーパーの発行など、さまざまな活動を行っています。「100年後も雪国であるために」という理念のもと、地域の暮らしや文化を発掘しつなぎ合わせることで、未来にその文化を残していきたいと思います。
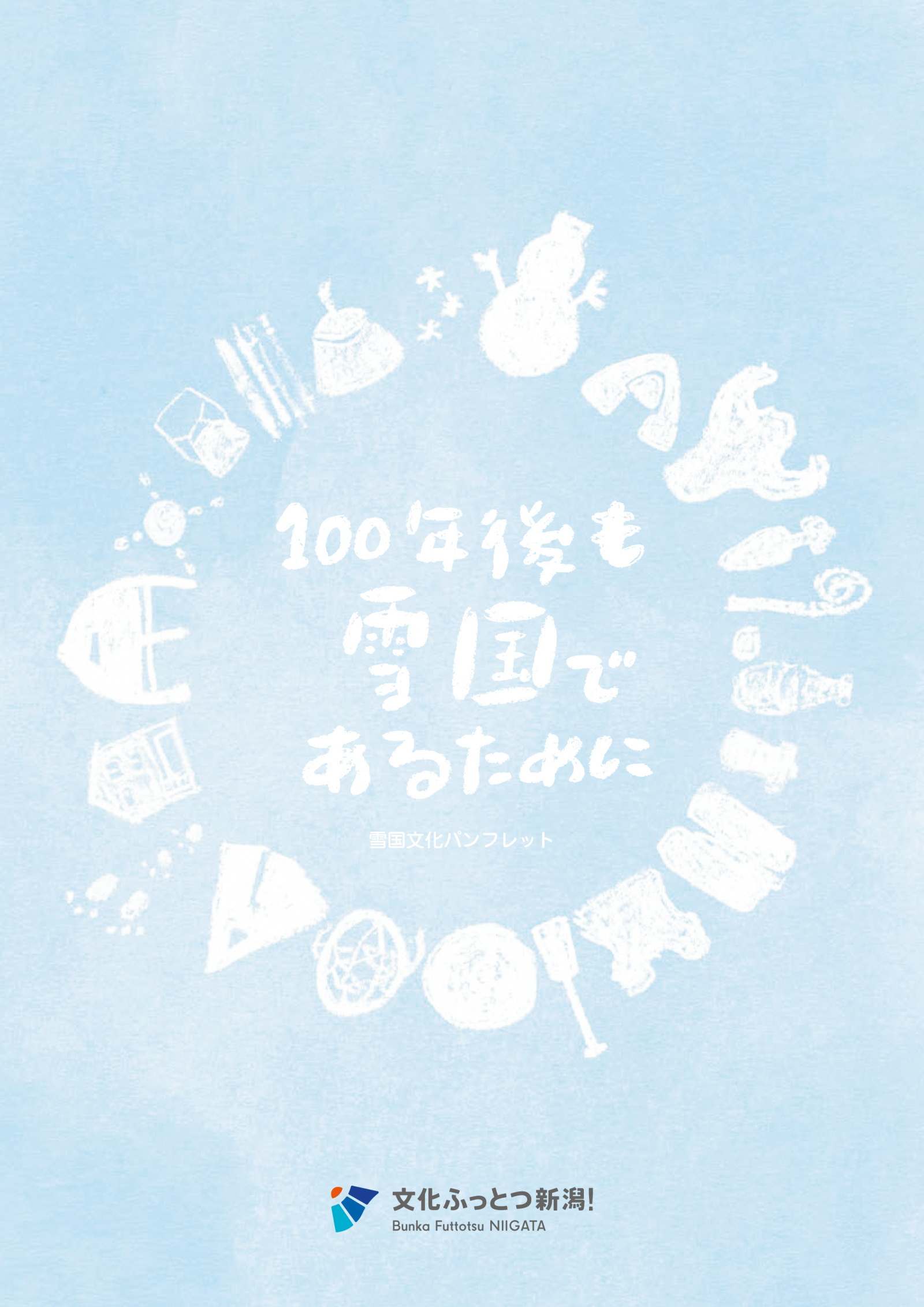
このアクションを続けるために、大切にしていることは?
雪国の未来のために何ができるかを考えること。
ANTCICADA 共同創業者・関根賢人

「昆虫食」のネガティブなイメージを払拭し、魅力を伝えたい。
『ANTCICADA』が目指すのは、「動物も、植物も、虫も、分け隔てなく向き合える社会」です。特に、昆虫食の魅力を伝える活動に重きを置いていて、この春、東京・日本橋馬喰町にレストランを開店します。提供するのは、コオロギで出汁をとった「コオロギラーメン」と、昆虫を使ったコース料理。昆虫の魅力を最大限引き出した食体験をつくり、昆虫への世の中のイメージに一石を投じていきます。

“ゲテモノ”と思われがちな昆虫ですが、実は食材としての可能性に溢れています。たとえばコオロギは、脂肪分が少なくタンパク質が豊富。雑食なので私たちが普段捨てている食材を喜んで食べてくれるし、餌によってコオロギの風味も変わるため、調理の幅も広がります。ビール粕で育てたコオロギを原料に製造した「コオロギビール」は、豊かな香りと旨みを味わえる「循環型ビール」として評判を呼びました。ほかにも、「コオロギ醤油」や「コオロギドレッシング」といった商品を開発しています。

そんなコオロギですが、養殖における飼料効率は牛や豚の6分の1。飼育面積も約15分の1で済みます。環境負荷が低く、持続可能性が高い食材なのです。需要が高まり養殖の生産効率が上がれば、タンパク源の低価格化が進み、栄養不足に苦しむ子どもたちを少しでも減らしていけるかもしれません。ゆくゆくは、各家庭にコオロギ養殖キットを普及させて、タンパク源を自給自足できる仕組みをつくれたら、と夢想しています。

ただ、「不足していく食料の代替品として虫を食べましょう」というのは私たちの本意ではありません。私たちはもっとポジティブに、”未知の食材を口にする冒険”をより多くの人に楽しんでもらいたいのです。虫を食べるという体験をすると、身の回りのあらゆる生き物がおいしい食材に見えてきます。地球は未発掘の味覚の宝庫。これからも一生を懸けて、地球を味わい続けていきたいですね。

このアクションを続けるために、大切にしていることは?
自らが楽しみながら、真に魅力あるものを届けること。
IDEAS FOR GOOD 編集長・加藤佑

社会課題への実践者を増やす、アイデア満載の解決策を発信。
『IDEAS FOR GOOD』は、社会課題の解決に向けた世界中のクリエイティブなアイデアを紹介するウェブマガジンです。世の中にポジティブなニュースの流通量を増やしたいという想いから生まれ、「解決策」に光を当てた記事を掲載しているのが特徴です。そのため、記事の切り口はテクノロジーやデザイン、アート、マーケティング、広告などさまざま。社会課題に関心がない方にも、自身の好きな分野に関する記事として読んでもらえ、新たな接点が生まれる可能性を秘めています。デザインに関する記事を読み、「デザイナーの立場からの社会貢献もできるんだ!」と知り、自分のスキルでできることに興味を持ってもらえたらうれしいです。

そして、メディアを運営するうちに、情報を伝えるだけでなく、私たち自身も優れた事例をつくりたいと思うようになりました。ウェブ上での発信やメディア運営を通じて蓄積された知見やつながりを活かしてできることは何か。そんな想いから、今年3月に開始したのが『IDEAS FOR GOOD Business Design Lab』です。これはサスティナビリティやSDGsなどに関する商品やサービス開発を検討している企業向けの会員制プラットフォームで、世界の最新情報の提供や視察ツアーのアレンジなどのインプット(情報収集)から、プロジェクトの立案やPRといったアウトプット(アクション)までを一貫して支援していくものです。『IDEAS FOR GOOD』に掲載する事例を、企業と共に創出することを目指しています。

そして企業だけでなく、これからは読者の皆さんも、ぜひ情報の受け手から発信者側になっていただければと。現在は読者と企業がコラボするワークショップなども行っています。実は『IDEAS FOR GOOD』のライターのほとんどが、もともとは読者でした。「自分でも何かできるかもしれない」と感じていただき、ソーシャルな取り組みへの一歩を踏み出してもらえたらと思います。