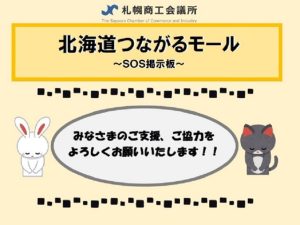今の時代、カフェを開業したいという若者はどれくらいいるのだろうか。ネット上では、カフェ経営の難しさや失敗談を語る記事も多く見かけられる。
そう語るのは、カフェ空間のシェア活動やコミュニティの場づくりを手掛けている山納洋さん。たしかに個人店の経営はリスクが大きいが、その一方で山納さんの周りには楽しそうにカフェや喫茶店、バーに関わる人たちがたくさんいる。
日替わりオーナー制の店、週末だけ開店する店…。重いリスクを背負わなくても好きなことを始める方法はいくつもある。山納さんが語る実例を交えながら、カフェ経営の“自由なカタチ”を紹介したい。
数年ごとに店主が入れ替わる喫茶店「ニューMASA」
ニューMASAは、大阪市北区・中崎町にある純喫茶。店名も内装もほとんどそのままに、次の店主へバトンを渡していく“譲り店”というしくみで場を守っている。日単位・週単位でのシェアではなく、年単位で店主が代わるという工夫が新鮮だ。
「譲り店」ニューMASA | 店主がいつか“卒業”できる、持続可能な喫茶店。
日替わりマスター制のバー「Common Bar SINGLES」
山納さん:「2001年から2004年まで僕は、コモンバー・シングルズのオーナーをしていました。この場所は以前、Bar『SINGLES(シングルズ)』という名前で1999年にオープンした店でした。お店が開業してから1年くらいして2代目マスターに代替わりしていて、僕が初めて訪れたのはその時代です。常連として通っていたのですが、シングルズが店を閉めるという話が出たときに譲り受けました。この例も“譲り店”と言えますね」
シングルズは、バンド「フィッシュマンズ」の音楽を流す、フィッシュマンズ好きが集まる店だった。山納さんが足を運び始めたのは2000年。扇町界隈のバーやカフェで「Talkin’ About」というトークサロン企画を手掛けていたことから、その会場候補になるだろうかと覗いてみたのがきっかけだったという。自身もフィッシュマンズのファンだという山納さんは、2代目マスターと会話が盛り上がりすぐに意気投合した。
では、なぜ山納さんが店を譲り受け、オーナーを務めることになったのだろうか?
山納さん:「シングルズは、音楽を愛する人たちがゆるやかにつながっていく、心地の良い空間でした。ただ、店を維持していくことは、経済的な問題だけではなく時間的・精神的にも簡単なことではありません。そこで、店を閉めると聞いたときに考えたのが、同じ想いをもったメンバーが交代でカウンターに立つという方法です。マスターになりたい人を募り、日替わりマスター制の店として再生させる決心をしました」
こうした動きの中、時間切れのようなかたちで2001年2月にシングルズは閉店した。しかし、マスター候補が集まってミーティングを重ね、2001年5月にはコモンバー・シングルズとしてオープンまでこぎつけた。
元々のオーナーやマスター、お客さんたちと、新しく店を始める人の間に関係性があれば、店舗経営は実現しやすくなるのかもしれない。その反面、「いつも周りに応援されることばかりでもない」と山納さんは付け加える。
山納さん:「多くの人に愛されてきた店を継ぐというのは、落語家の襲名みたいなところがあると思うんです。どうしても、過去の歴史との比較をされてしまう。『あんたの芸はまだ先代には及ばんなぁ』と。店名を残して継ぐには、覚悟も必要ですね。それでも、シングルズ時代からの常連さんには助けられたし、コモンバー・シングルズになってから新しいお客さんも増えました。継いでいくことの難しさと面白さ、そのどちらも実感しましたね」
コモンバー・シングルズは、山納さんがオーナーから退いた後も有志によって営業を続けてきたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響から2020年11月にやむなく閉業している。カウンターだけの小さなバーで、密を避けて営業することはできなかった。ただ、自然と会話が弾むような距離の近さから、ここでさまざまな縁が生まれ、面白い出来事が起きてきたのは間違いないだろう。
リスクをシェアして運営できる表現空間「common cafe」
山納さんがシングルズを訪れるきっかけとなった「Talkin’ About」も、大阪ガスの仕事で担当していた「扇町ミュージアムスクエア」(略称:OMS)の企画・プロデュース業務から派生したものだった。OMSは小劇場やミニシアターなどを備えた施設。関西小劇場のメッカと言われ、文化の発信地となっていた。
山納さん:「OMSを拠点にしていた演劇・音楽関連の表現者たちが活動できる場がほしいなと。コモンバー・シングルズでもOMSで育んできたものを継承していこうという活動はありました。しかし、12席ほどしかないバーの空間では手狭なため、50人くらいお客さんが入れるような場所をつくろうと思ったのです。それが、日替わりマスター制のカフェ『common cafe(コモンカフェ)』です」
会社員として働きながら、しばらくはバーとカフェの経営を続けていた山納さん。日替わりマスターが店の管理をしてくれているとはいえ、キャパオーバーになっているのを感じていた。そこでバーの経営は手放し、カフェに専念することに。
多額の初期費用を貯めなくても、仕事を辞めなくても、日替わりカフェならマスターになれる。副業・兼業を解禁する企業が増えてきた昨今、平日は会社員・土日はカフェオーナーといった働き方も選択しやすい時代になってきたのではないだろうか。
形態を変えながらも継続する週末シェアカフェ「六甲山カフェ」
ニューMASAの4代目店主として現在店頭に立っている古家慶子さんは、「六甲山カフェ」というプロジェクトを長年続けていた。
コロナ流行以降、茶屋自体は休業しているものの、有志メンバーによって週末カフェは継続されている。そんな六甲山カフェに、実は最近進展があった。茶屋の売店だった母2階建ての母屋も、六甲山カフェメンバーで使えることになったのだ。山納さんは「大谷茶屋を託されつつある」と話し、次の担い手によって茶屋も再開できたらと夢を描いている。現在、サテライトオフィスのように仕事場として利用しながら売店を開けてくれる人を募っているそうだ。
みんなで分担する文化があれば、場を守り続けられる
山納さん:「沖縄には、古くから『共同売店』という相互扶助で成り立つ店があるそうです。共同売店とは、地域住民が共同で出資・運営する売店のこと。交通手段が少ない地域でも、住民が食料品や日用品など、生活に必要なものを入手できる店がないと困ります。そのため、みんなで協力し合って店を支えているといいます」
共同売店の利益は、配当や医療費・学費への還元など地域のために使われるそうだ。ビジネスとして儲からなくても、店の存在が人々に必要とされていれば存続できる。
山納さん:「common cafeを始めるときにも、共同売店のようなイメージをチラッと思い浮かべました。助け合いで成り立つ店。ただモノを売ったり場所を提供したりするだけではなく、さまざまな人たちをつなぐコミュニティとしての機能も、こうした場所に生まれるのではないでしょうか。六甲山カフェの売店も、ビール・ジュース・お菓子を販売する共同売店として開く予定です」
もちろん、脱サラして自分の好きなことを徹底的に追求するのも良いだろう。ただ、方法はひとつではない。考え方次第で、一歩踏み出すための敷居は下げられるのではないだろうか。
写真提供/山納洋さん
齊藤 美幸|まちと文化が好きなライター。広告制作会社での勤務を経て、2020年からフリーランスとしてソトコトオンライン他で執筆中。地元・名古屋を中心に、都市の風景や歴史、地域をつくる人の物語などを伝えている。