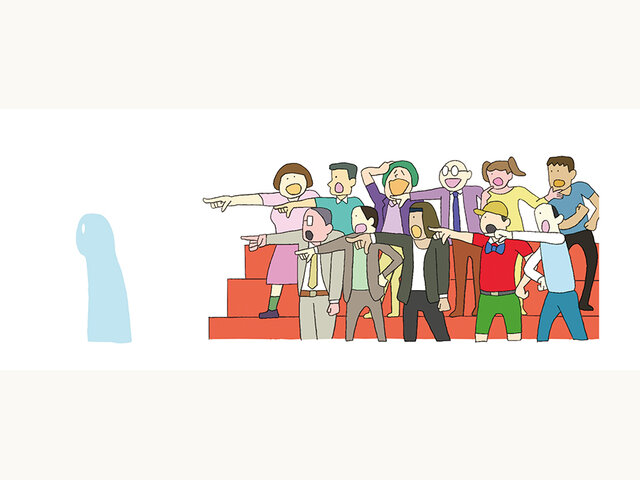僕は「やめろや!」と言うのも負けた気がして、言いたくないと思った。というか、そもそも意味がわからなかった。つるべに似ているって良くないことなのだろうか。「似てへんし!」と返す自信もなかった僕は、まだ知ってる悪口も少なかったので、「チービ!」と返した。するとHはイラツいた顔をして、「ブース!」と言った。そういうことかと思った。二人はまだ鶴瓶師匠の格好良さを知らないのだった。
それからブスとチビによる泥試合は、1年以上続くことになった。ようやく収まったのは5年生になる頃で、その頃には「ブス」と「チビ」というラベルは、お互いのコンプレックスへとしっかり成長していた。僕らの間には「俺も言わないから、お前も言うなよ」という無言の停戦協定のようなものが敷かれ、無視をしあっているうちに、互いが互いの関心から消えていった。
Hがその後どうしたのかは転校したので知らないが(健闘を祈るが)、僕が「ブス」という呪いを昇華できたのは、中学生になってからだった。中学とか高校に入ると、急に恋愛バラエティショーのセットに座らされたような毎日になる。フロアには取っ替え引っ替え付き合っては別れる男女が現れ、なぜかその話を取材してまわる人間も現れる。そんな中で、「ブス」を背負わされたゲイの僕は、「非モテ」という雛壇を見つけた。人気者たちの恋愛話にひねくれた茶々を入れてみんなを笑わせたり、時には安心させたりするその席は、全然悪くないどころか、僕には格好良くさえ見えた。そこには文化があり、同志との連帯があった。映画『モテキ』が流行った時には、主人公の気持ちが「わかる側」として楽しめたことに誇りを感じたし、人気者たちに一泡吹かせてやったような気にもなった。僕にとって「非モテ」は矜恃ある席であり、居場所だった。
だけどそんな僕も恋愛願望がなかったわけではない。だからこの数年はジムにも通うようになったし、仕事も頑張ってきた。いろんな人との関わりの中で人間関係の妙を学び、色気ってなんなのか、なんてことも真面目に考えるようになった。それらすべてが自分にとっては「非モテ」らしい愚直な努力だったけど、僕と恋愛との距離は、そうして少しずつ近づいていった。
飲み会で「モテるでしょ〜?」と言われたのは、そんな時だった。僕は「誰に聞いてるんっすか!」と笑ってしまい、いつもどおり雛壇からツッコミを入れる要領で「そんなわけあるかい!」と返したけれど、ひとつもウケることはなくて、あ、こういうのはもう冗談にならないのかもしれないと思った。僕は以前とは同じ場所に座っていないのかもしれなかった。
その日の帰り道で南海キャンディーズの山ちゃんのことを思い出した。山ちゃんは妬みを源にして笑いをとってきた人だけど、そんな彼も今や、すっかり妬まれる対象になった。山ちゃんは蒼井さんと結婚する時、幸せになっていいのかずっと悩んできたと、涙ながらにラジオで語っていたけれど、なるほど、望んでいたものに手が届くということは、不幸が幸に反転するような単純な話ではないのかもしれない、と僕は思った。それは、かつて希望だったものを手放すことであり、これまでは思いやりだったものが、思い上がりだと言われてしまうことでもある。
僕は今も別段モテはしないけど、かといって「非モテ」に座っていても滑り続けるのかもしれないし、それはもしかしたら僕が変わったというより、社会が変わっただけなのかもしれない。しかしいずれにせよ、新たな居場所を探すほうがいいのだろうと、夜道でひとり思った。次は「モテ」とか「非モテ」とかそんな線上には立っていなくてかっこいい、笑かすのが上手な人になりたい。ちょうど鶴瓶師匠のような人に。
文・太田尚樹 イラスト・井上 涼
おおた・なおき●1988年大阪生まれのゲイ。バレーボールが死ぬほど好き。編集者・ライター。神戸大学を卒業後、リクルートに入社。その後退社し『やる気あり美』を発足。「世の中とLGBTのグッとくる接点」となるようなアート、エンタメコンテンツの企画、制作を行っている。
記事は雑誌ソトコト2021年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。