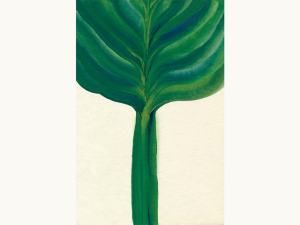樹々たちがたくさん水を吐き出して、あたり一面まっしろな霧に包まれる朝が続いた。霧がゆったりと山にまとわりつくその姿は、まるで白い竜のようだ。何頭の白竜が空に立ち昇った頃だろう、ふうっと風に捕まって、くるりくるりと空を機嫌よく舞うものたちがいる。「最後の葉っぱたち、宙を舞う」。今日はそういう季節の日なのだと覚えておこうと思っていたら、また別の日は、朗らかすぎる黄色い陽気が降りてきた春のような日に、本当の春と間違えたのか、大量のてんとう虫が嘘みたいに輝きながら飛び交った。そんな日もあれば、妻が「雪虫」と名付けた、こんまい雪が、虫のようにふわふわと下から上へと飛んでいった。いろいろあって一番嬉しかった日には、お天気雨が降って、どこもかしこも虹が懸かっているような、いまいるここが極楽だった。どれも朝ごはんを食べながら、同じ席の同じ窓から見た景色だけれど、秋と冬の狭間に、果てしなく細やかな季節を届けてくれる。
あっ、いけない。お稲荷さんの当番を忘れるところだった。月の終わり、村のお山のてっぺんに神社のお掃除に上がるのだった。一升瓶に水をいっぱい汲んで、熊手と空の米袋を抱えて山に入る。登りがてら、こんもりと積もった落ち葉を掃いて道をつくっていく。杉ん葉は薪ストーブの着火材として使えるので米袋に大量に入れて持って帰る。それにしても、山なので、落ち葉があるのは自然なことなのだけれど、なぜだろう、掃いてすっかり土の地面が現れると、ここは山道ではなく、まさしく参道なのだと思えてくる。赤ちゃんが生まれてくる道も産道と呼ぶけれど、山の落ち葉を掃いているだけなのに、ましてや僕は男なのだけれど、躰の中にある道を同時に清めている気がしてくる。てっぺんに着くと、お宮の周りもすっかり綺麗にして、柏手を打って挨拶をする。お稲荷さんに、祇園さん、ぐるりお宮を回って、鹿倉山に、春日さんに。すっきり掃いて雑巾掛けした空間は、空を突き抜けて天に繋がった気がする。
村に赤ちゃんがやってきた。とても小さな赤ちゃんを抱かせてもらった。まだはっきりとは見えていなさそうな小さな瞳に。何を聞き取っているんだろう小さな耳に。くぱあと息を吐き出すたびに真っ赤になった顔色が、元に戻っていくほんの瞬間に、にっこり笑っているように見えたり。小さな指が何をつくるのだろう。久しぶりに自分の小さい頃の写真を見てみた。父親に抱かれて、どこともない、なんともない表情をしている小さな自分がいる。なんというか、ピアノを弾いたり、こういう風に文章を書くことになるとは思わへんよなあ。この子がなあ。不思議やなあ。
どどど、どさっ、重々しい音が母屋の大屋根から落ちてきた。早くもどっさり雪がやってきた。すっかり葉を落とした樹々にふわふわ泡のような雪がびっしり覆いかぶさって、いつか海の中で見た珊瑚礁のよう。雪が解けると、背の高い草はこの寒さですっかり消えるように居なくなっていくけれど、たんぽぽのように地面に這いつくばって広がる草は生き生きとしていて、それに赤や黄や緑のなんとも変わった色をしているので、草の上を歩いているだけで海の底を歩いているようにも思えてくる。なんて、山におるのか海におるのか、わからんようになった頭で、ぼんやりと未来のことを考えてみたりする。冬のしんと静かな日々が増えて、外の音よりも自分の中のいろんな音が聞こえて、どれも小さなささやきなので耳を澄ませてみる。呼吸をしている。心臓は動いている。村の集まりで男たちだけで酒を交わした。「かっちゃん、村おこしとか、そういうのはここではもういいんや。ここだけは別でいいんや。わかるか。今おるわしらが機嫌ようやっていこうやないか。機嫌よう毎日やってるのが一番ええ」。そう、機嫌よく。自分を機嫌よく。毎朝、目覚める度に、まるで新しい朝だということに気づいてあげられれば、自分を歓ばせてあげられれば、極楽は目の前にある。ハマちゃんの口癖、「あるんだから」、そう、あるんだから。すでにあるんだから。