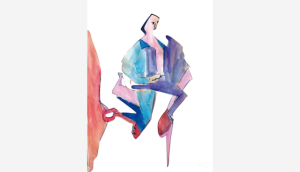2019年までは医師として東大病院に勤務し、2020年から軽井沢病院へ家族と共に引っ越した。東京での暮らしは刺激も多く友人も多く、知的には何も不満のないものだったが、体は些細な違和感を感じ続けていた。それは暮らしや生活が、あまりに分断化され細分化され過ぎていて、「生きている」というリアルな生のリアリティを感じにくいことの裏返しでもあった。たとえ自分が全身全霊で生きていなくても、自分が成熟していかなくても、日々は漠然と流れていく。巨大なシステムは自分と無関係に刻々と動き続けていく。そうした生活の足元に対しての違和感。確かに東京での生活は便利だ。ただ、自分の何かが根本的にずれ続け、断層だけが確実に広がっている違和感。頭では正体を把握できないのだが、体は鋭敏に感じ取っている。好きだった東京での暮らしも、なぜだか少しずつ嫌いになろうとしていた。

2歳の子どもと妻と自分という三人での核家族の暮らし。昔は、温かい地域社会のつながりがいろいろな問題を受け止めていた。確かにそう思う。地域とのつながり、温かい心の交流が自然に息づく町がどこにでもあった。映画や漫画で描かれる牧歌的なゆったりとした暮らし。自然と強く結びついた美しく豊かな暮らし。時には自分の都合で美化されながら、脳内イメージはどんどん膨らんでいく。ただ、そうした人と人との近い距離感が、不自由や差別を生んだこともあった。関係性の近さや距離の狭さの弊害も大きかったからこそ、人々はお互いに距離を取るような都市生活をせっせとつくり続けてきた側面もあったのではないだろうか。人と人、人と自然との距離が近過ぎたからこそ、その間に人工物を緩衝材のように挟み込むことで、わたしたちは自然界の中に文明という名の人工世界をつくり上げ、人間界をつくろうとした。では、東京などの巨大都市は、人間界としての完成形なのだろうか。

2020年のコロナ禍は、「social distance(社会的距離)」を取るように言われ、わたしたちは人と人との「距離」の意味を考えるようになった。それは感染防御を入り口としたものだったが、人同士の距離だけではなく、人と自然との距離を考えることにも本質があった。自分は、コロナ禍の前から(具体的には2011年3月11日から)、「暮らし」という、仕事や家族を支える社会基盤を切実に考えるようになった。医療者としての仕事のこと、生活者としての暮らしのこと、家庭人としての家族内での対話や子どもの教育のこと。あらゆる生活の基盤をいま一度考え直してみようと思い、軽井沢に引っ越した。今までの暮らしから、自分は「全体性」が失われていると感じていたからこそ、人生の後半は全体性を取り戻す時間にしたいと思った。自分が取り組んでいる医療、愛する芸術や文化、学びを深める教育、寝て起きて日々を暮らす生活の場、自分を支える家族や友人。そうした自分を構成するすべてのものがバラバラにならず、全体性を取り戻すとはどういうことか。自分なりに試行錯誤しながら、人生を生き切りたい。

個を深めていくこと。個と場の関係性を更新していくこと。そうしたシンプルなことを手掛かりにしながら連載させていただきます。貫通するテーマは「いのち」です。「いのち」というフィロソフィー(哲学)を共有する場を、共に考えていきたいと思っています。