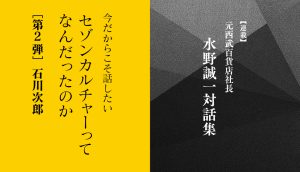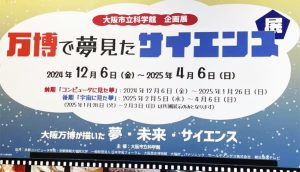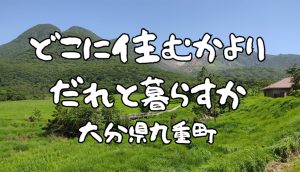「湯湯婆」これなんだ?
ゆゆばあ?
皆さんも知っているあのアイテムですよ!
こんばんは😊🍀
ホットカーペットで…🐈🐈⬛
∧_∧
⊂´⌒つ* -_-)っ ゴロゴロ本日から湯湯婆を使います😊
小さいのは…
琥珀と陽葵のお布団に入れて
暖かくしておきます。先日漬けた白菜柚子漬けと
蕪の糠漬け。
美味しくできました😊🍀今宵も暖かくされて
お過ごしくださいませ🌃🌛 pic.twitter.com/nnlmS1Jwkw— 茶とら。 (@koukun_hina_) December 17, 2021
答え:ゆたんぽ
湯たんぽあったかいかな。おしりがぽかぽか。気に入ってきたね。 pic.twitter.com/IQToHMUx9O
— たけのこスカーフ (@takesuka) October 19, 2021
湯湯婆の由来
低温やけどに気を付けて
参考:消費者庁(https://www.caa.go.jp/)
参考:金沢くらしの博物館(https://kanazawa-museum.jp/minzoku/index.html)