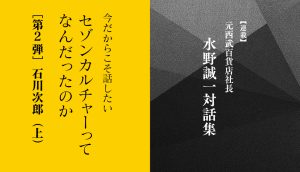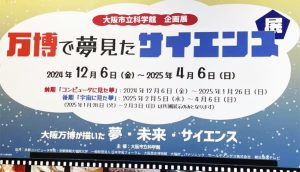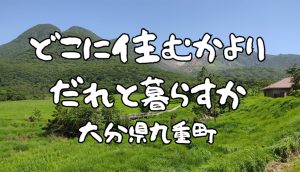今日は「漬物の日」!
毎月21日が「漬物の日」となったのは、毎年8月21日に愛知県の萱津神社で「香乃物祭(漬物祭)」が行われているからだそうです。これにならい、漬物業界では毎月21日を「漬物の日」と定め、さらなる漬物の普及を目指すようになりました。

萱津神社は、日本で唯一の漬物の祖神といわれる「鹿屋野比売神(かやぬひめのかみ)」を祀る神社で、漬物発祥の伝説も残ります。まずはその伝説をご紹介します。
むかし、萱津神社を祀る人びとは五穀豊穣を祈り、ウリ、ナス、蓼などの野菜や海の藻塩を神前にお供えしていました。しかし、月日が経てば、お供えした食べ物は腐ってしまいます。あるとき、そんな様子を惜しんだ人が社殿のそばに甕(かめ)を置き、お供えした野菜や塩を入れました。すると、その中で程よい塩漬けができあがったそうです。当時の人びとは、この雨露にあたっても変わらない不思議な味がする食べ物を神様からの贈り物として、万病を治すお守りにしたといいます。このことが、日本の漬物のはじまりといわれています。

この故事が由来となり、萱津神社では漬物文化の興隆を祈る「香乃物祭(漬物祭)」が行われるようになりました。当日は、一般参拝者も参加できる「漬け込み神事」や、全国各地の漬物業者による「漬物即売会」などが開催されるそうです。(※2021年の開催については、公式ページにて随時ご確認ください。)
<参考>
漬物祖神萱津神社「由緒」https://sites.google.com/site/kayatsujinja/introduction(2021/2/14)
全日本漬物協同組合連合会「毎月21日は漬物の日」https://www.tsukemono-japan.org/tukemono_day21/index.html(2021/2/14)
地域の暮らしをあらわす、漬物文化
萱津神社の伝説にもある通り、日本でも歴史ある漬物文化。国内でも、地域ごとの気候や風土によって、作られる漬物の種類もさまざまです。
そこで今回は、全国各地の漬物を取り扱う、東京・千駄木の漬物専門店「やなぎに桜」の店主・柳沢博幸さんに、各地の漬物についてお話をうかがいしました! 漬物の選び方や楽しみ方も教えていただいたので、ぜひ参考にしてみてください。

ワインやウイスキーにも!おいしい漬物の選び方

築地の漬物問屋から始まり、漬物販売に携わって30年以上という柳沢さん。食べた漬物は、なんと1,000種類以上にものぼるそうです。全国各地のさまざまな漬物を食べ続ける柳沢さんに、まずは各地域ごとの特色について教えてもらいました。
柳沢さん「たとえば、お米が収穫できる地域は麹漬け。北海道の『石狩漬』や、石川だと『かぶらずし』などですね。そこからもう少し下におりてきて、宮城、栃木、茨城、千葉あたりだと醤油漬けが多かったり。中国から醸造技術が早くに伝わった近畿あたりは酒粕系で、『奈良漬け』が有名ですよね。あとは九州なら『高菜漬け』や鹿児島の『壺漬け』とか。これらも一部なので、ほかの漬物もまだまだあります。今は全国各地の漬物がどこでも食べられるので混在していますが、地域の歴史や風土によって、使う野菜や漬け方の違いがありますね」

長いあいだ、保存食として食べられてきた漬物。その土地の歴史や気候、暮らしに密着して根付いてきた文化だからこそ、各地域ごとに特色が生まれているようです。さらに柳沢さんによると、同じような漬物でも地域ごとに違いが生まれるのだそう。
柳沢さん「醤油漬けは、岩手や青森あたりでも同じようなものがあります。でも、南から北に上っていくごとに味の濃さや野菜の干し加減が変わっていて、味わいも違うんですよ。たとえば、千葉では歯切れよくパリパリしているのに、青森の方はぶよぶよしてるとか、そういう変化がけっこうあって。その違いもおもしろいですよ」

似たような漬け方をしていても、地域ごとに味や食感が変わるというのは興味深いですよね。地域によって温度や湿度が違うほかにも、味の好みの違いもあるのかなあ?などと想像が膨らみます。漬物を食べながら、そんなふうに各地の暮らしを思い浮かべてみるのもおもしろそうです。
しかし、長年さまざまな漬物を見極めて仕入れている柳沢さんですが、“郷土の味”にはかなわないと感じているとか。
柳沢さん「よくお客さんから『私は〇〇県出身なんだけど、〇〇の漬物はないの?』って言われることもあって。でもたぶん、その方が地元で食べた味と、うちで仕入れるものの味ってやっぱり違うんですよね。郷土の味とか思い出の味にかなうものって、絶対ないんですよ。だからうちでは、あえて各地方の代表的な漬物を置くようにしています」
「国産、無添加、おいしい」が大前提
柳沢さんが漬物選びの条件に掲げるのは、「国産」「無添加」「おいしい」の3つ。一般に販売されている漬物のなかには、着色料や保存料が入った漬物も多いといいますが、「やなぎに桜」では、できるだけ添加物の入っていない、国産の原材料を使った漬物を仕入れるようにしています。

それは、日本で長く続いてきた漬物の伝統を守りたいという柳沢さんの思いがあるから。昔の漬物には、当然添加物は入っていません。それが現在まで続いてきたということは、味もおいしく、そして体にも良いからこそ。今では添加物が入っていない漬物を探すのにも一苦労ですが、この先も日本の漬物文化が続いていくために、国産無添加のおいしい漬物にこだわり続けています。
柳沢さんは「国産」「無添加」ということに加えて、家庭で食べる漬物を選ぶときのポイントも教えてくれました。
柳沢さん「やっぱり、時期のものがいちばんおいしい。自家製のぬか漬けも、大根、にんじん、白かぶ、きゅうりの4種類を漬けていますけど、この時期のきゅうりは中が黒くなっていたり、スカスカしたものもあります。やっぱり夏場のほうが、きゅうり自体もおいしくなりますから。今だったら大根、かぶなどの根菜系、春なら山菜、夏場はウリ系が旬です。旬の時期に旬のものを味わってもらうほうが、『おいしい』と感じてもらえると思いますね」

ワイン、ウイスキーとの合わせ方も!
そして、漬物の食べ方は和食に合わせるだけではありません。漬物をお酒のアテにして楽しむ人も多いと思いますが、最近ではワインやウイスキーなどの洋酒と日本の漬物を組み合わせるお店も増えてきているとか。
柳沢さん「最近は、表参道や渋谷あたりのワインのお店でも、うちの漬物を使ってくれていたりするんです。お店の方と実際にお会いして、私から希望にあわせて提案もします。だいたいワインだと、甘酢系の漬物なら間違いないと思いますね。あとは、意外と醤油漬けや奈良漬けも合わせやすい。ウイスキーなら、味噌漬けがけっこう合いますよ」
もちろん、ごはんと漬物という定番の組み合わせも最高!なのですが、新たな魅力を引き出す意外な組み合わせで楽しむのもワクワクしますよね。歴史が長いからこそ伝統的な食べ方にこだわってしまいがち。しかし逆に言えば、まだまだ内に秘めた魅力があるのかもしれません。
ぜひお気に入りを見つけて
漬物は、ごはんのお供はもちろん、食事の箸休めやお酒のつまみ、さらにはお茶うけにもなります。ライフスタイルやいつもの食事に合わせて漬物を選ぶも良し。もしくは、お気に入りの漬物を見つけて、それに合う食べ方を研究するも良し。漬物はふだん買わないという人も、今日はぜひ、漬物専門店やスーパーの漬物売り場をのぞいてみてください! 新たな出会いがあるかもしれません。
「やなぎに桜」の人気No.1はこれ!

ザーサイの浅漬け(100g 216円)
「やなぎに桜」で取り扱っているのは、ザーサイをまるごと1個漬けたものと、食べやすい大きさにスライスした2種類。ちなみに写真は、まるごとを半分にカットしたもの。商品自体の珍しさもありますが、人気の秘密はやはり味。白醤油をベースにハーブや香辛料を掛け合わせ、深みのある独特な味わいになっています。ごはんやおかずに合わせるだけでなく、このまま単体でも箸が進みます。お酒との相性も◎。ぜひお試しあれ。
取材協力

漬物専門店「やなぎに桜」
住所:東京都文京区千駄木2-33-6
TEL:03-5834-0602
営業時間:10時〜19時
定休日:毎週水曜
公式サイトはこちら